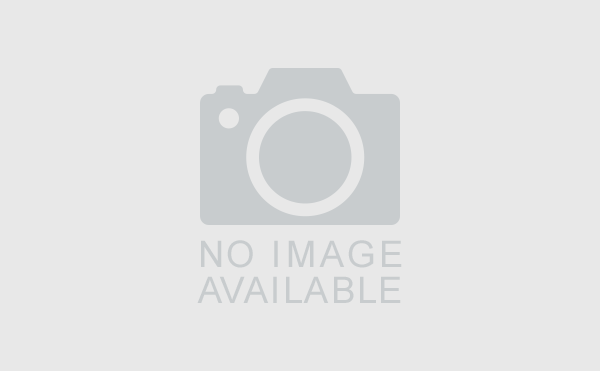「部活やクラブで一生懸命頑張っているのに、なぜか思うように成長しない」
「ケガが多い」
「動きがよくならない」
そんな悩みを持つ学生アスリートは少なくありません。
その原因、実は生活習慣の乱れにあるかもしれません。
スポーツはあくまで“身体を使った表現”です。だからこそ、スポーツ中だけを頑張っていても、普段の生活の姿勢や習慣が乱れていれば、パフォーマンスの向上は望めません。
この記事では、「スポーツと生活習慣の関係」について詳しく解説します。
スポーツと学校生活・私生活は切り離せない
「スポーツは頑張ってるけど、学校ではダラダラ」
「授業中は寝てばかり」
そういった生活をしていると、せっかくの練習も十分に活かされません。
たとえば、授業中にずっとうつ伏せで寝ていたり、背もたれにだらりと寄りかかって座っていたりすると、体幹部の筋肉はほとんど使われません。
この状態が習慣になると、姿勢保持に必要な筋肉がサボり始め、いざスポーツをする場面でも正しい姿勢を保てなくなります。
つまり、「悪い姿勢が当たり前」になってしまい、スポーツ中のフォームの崩れや動作のエラーにもつながるのです。
「今の体」は日々の習慣が作っている
私たちの身体は、“今までの積み重ね”でできています。
食事、睡眠、運動、姿勢、勉強時間中の座り方――すべてが「今の体の状態」に影響を与えています。
例えば、1日の中でスポーツをしている時間はせいぜい2〜3時間。
それ以外の時間、つまり学校の授業や通学、家庭での時間の方が圧倒的に長いのです。
この長い時間をどう過ごしているかが、スポーツ中の姿勢・動き・回復力・集中力に直結します。
姿勢はパフォーマンスを左右する
姿勢が悪いと、呼吸が浅くなり、体幹の安定性が低下し、関節の動きにも偏りが出ます。
これは、単に「見た目の問題」ではありません。例えば、胸が丸まっていると腕の振りがうまく使えなくなったり、骨盤が寝ていると脚の力が伝わりにくくなったりします。
また、日常的に悪い姿勢をしていると、脳がその状態を“正しい”と認識してしまい、競技中にもそのままの姿勢を再現してしまうのです。
スポーツの成長を支えるのは、日々の「当たり前」
「頑張っているのに結果が出ない」と感じたとき、技術やフィジカルトレーニングだけを見直すのではなく、まずは日常生活の“当たり前”を整えることが大切です。
たとえば…
- 授業中、背筋を伸ばして座る意識を持つ
- 家ではスマホをダラダラ見ず、リラックスタイムと集中時間を分ける
- 食事は3食きちんととる
- 夜はなるべく早く寝て、睡眠時間を確保する
このような小さなことの積み重ねが、ケガを防ぎ、集中力を高め、回復力を早め、パフォーマンス向上を後押しするのです。
ウィスポでサポートしていること
ウィスポでも、学生アスリートをサポートする際には、トレーニングだけでなく生活面のアドバイスも重視しています。
実際、パフォーマンスの伸び悩みやケガの背景には、生活リズムの乱れ・栄養の偏り・姿勢不良が隠れているケースが非常に多いです。
状況によっては、無理なトレーニングではなく、日々の習慣によって生じた動作感覚のズレの擦り合わせや三半規管への刺激など、身体に備わる機能向上を目指すメニューから始めます。
それが結果的に、持続的な体づくりと競技力アップにつながるからです。
不良姿勢やイメージ通りの動作が実践できないと、いくら鍛えてもパフォーマンス向上に対してのマイナス要素が増えるリスクがあるため筋肉を鍛えるだけではダメなのです。
まとめ:競技力は、日常の積み重ねから
スポーツは、日常の延長線上にあります。
練習中だけ“頑張る”のではなく、日常から「整えている」選手こそ、長く成長を続けていけます。
「練習は誰にも負けないほどやっている」
そう思うなら、その努力を支える生活習慣も見直してみましょう。
姿勢・睡眠・食事・勉強時間中の過ごし方――
すべてが、あなたの「今の体」と「未来のパフォーマンス」をつくっていきます。