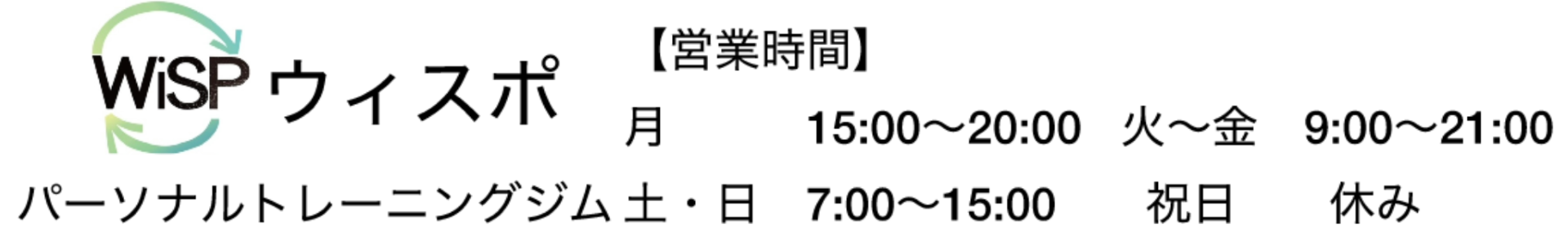陸上のレース終盤、フォームが崩れて失速する選手は少なくありません。
特に短距離・中距離では「最後までピッチ(足の回転数)を落とさないこと」が勝敗を左右します。
疲労によって脚が重くなっても、一定のリズムを維持できるかどうかは体幹の強さと働きに大きく左右されます。
疲労末期に起こりやすいフォーム崩れ
- 骨盤が下がり、接地の位置が後ろにずれる
- 上体が左右に揺れて腕振りが弱まる
- 足の回転数が落ち、接地時間が長くなる
- 無駄に上下動が増え、推進力がロスする
これらは単純な脚力不足ではなく、体幹が衝撃や反発を支えきれなくなることで生じます。
ピッチ走法を支える体幹の働き
1. 「体の軸」を安定させる
腰から骨盤まわりを固め、走りの支点をぶらさない。これがあるから脚を素早く前後に動かせる。
2. 「腿の引き上げ」をスムーズにする
脚を前に振り出す動きをサポートし、疲れても足の回転が落ちにくくなる。
3. 「骨盤のブレ」を防ぐ
左右のぐらつきを抑えることで接地が安定し、効率的に前へ進める。
4. 「腕振りと脚」をつなぐ
背中から腰にかけて上半身を支えることで、腕振りの力を脚へ伝えやすくする。
トレーニングの実践例
1. 基礎的な体幹安定トレーニング
- プランクやサイドプランク
- 腕や脚を動かしても姿勢を崩さないようにする
→ 疲労時にフォームが崩れにくくなる。
2. 動きを伴う体幹強化
- メディシンボール投げ
- バランスボールを使ったニーレイズ
→ 腕振りと脚の動きをつなげる練習。
3. 腿上げ・骨盤安定ドリル
- ゴムバンドを使った腿上げ
- 片足ブリッジで腰を安定させる
→ 脚の引き上げを速くし、骨盤の沈みを防ぐ。
4. 走りの中で鍛えるドリル
- Aスキップ・ミニハードル走
- 短距離のピッチ走反復(20〜40m)
→ 実際の走法に直結させ、疲労下でもピッチを保つ。
学生選手へのアドバイス
- 腹筋や背筋だけでは不十分。「骨盤を安定させる筋力」と「足を速く回すための体幹」が必要。
- 練習後の疲れている時に体幹ドリルを組み込むと、実戦での再現性が高まる。
- 強い体幹は怪我予防にもつながり、長く競技を続ける基盤になる。
まとめ
- 疲労末期にフォームが崩れるのは、脚よりも体幹の支えが弱くなることが原因。
- ピッチ走法を維持するには、体の軸を安定させ、腿の引き上げをスムーズにし、骨盤のブレを防ぐことが不可欠。
- 静的な体幹強化、動きを伴うトレーニング、走動作ドリルを組み合わせることで「最後まで回転を落とさない走り」が実現する。
疲労のピークでも走りの効率を保てる選手は、例外なく体幹が強く機能しています。体幹を「フォームを守るエンジン」として鍛えることが、勝負どころでの一歩の差につながります。