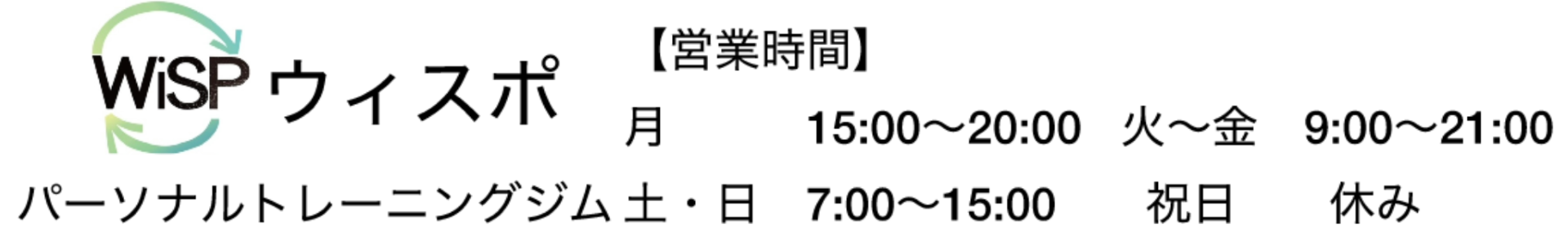スポーツに打ち込む学生は、練習や試合で体に負荷をかけ続けるため、知らず知らずのうちに「疲れ慣れ」の状態に陥ることがあります。
疲れ慣れとは、慢性的な疲労を感じながらも慣れてしまい、体や心に異常が出る状態です。
放置するとパフォーマンス低下や怪我、さらには健康への影響も出てしまいます。
ここでは、疲れ慣れのリスクとその防止・改善策を、スポーツ学生向けに整理します。
疲れ慣れのリスク
1. 慢性疲労状態
筋肉回復が遅れることで、練習後の筋肉痛や疲労感が長引き、パフォーマンスが落ちます。
自律神経が乱れ、練習中でもリラックスできない状態になりやすくなります。
2. ホルモン・免疫異常
コルチゾール(ストレスホルモン)が上昇すると、疲労回復や筋合成が阻害されます。
成長ホルモンやテストステロンが低下すると、筋力や骨の発達に影響し、免疫力も低下して風邪や感染症にかかりやすくなります。
3. 心理的リスク
イライラや抑うつ感が増すことで集中力が低下し、練習意欲も減少します。
長期間続くと燃え尽き症候群となり、やる気が持続せずパフォーマンスの低下を招くことがあります。
4. 生活習慣・事故リスク
注意力が低下すると練習中や試合中の判断ミスが増え、怪我や代謝異常の可能性も高まります。
疲れ慣れ防止・改善策
疲れ慣れを防ぐには、自分の体の状態を正しく認識することが重要です。
① 自覚チェック
睡眠の質を確認し、深い睡眠時間が十分かチェックします。
心拍変動(HRV)を測定することで、自律神経のバランスを数値化できます。
日中の眠気やパフォーマンスの変化を記録し、体調の変化に早く気づくことが大切です。
② トレーニングと休養のバランス
練習の強度と量を調整し、オーバーワークを避けます。
疲労が抜けるタイミングで高強度練習を組み、計画的に軽めの日や完全休養日を設けます。
③ 栄養・水分管理
タンパク質や炭水化物を適切に摂取することで、筋肉の回復とエネルギー補給を行います。
ミネラルや水分を補給して、疲労物質の排出や筋肉機能の維持をサポートします。
④ 心理的ケア
深呼吸や軽いストレッチで交感神経を抑え、リラックス習慣を身につけます。
気分やストレスの記録をつけて、心理状態の変化を可視化し自己管理につなげます。
まとめ
スポーツ学生にとって疲れ慣れは、パフォーマンス低下、怪我、体調不良に直結するリスクです。
慢性疲労やホルモン異常、心理的リスクが重なると、体も心も不調になりやすくなります。
日々の自覚チェック、休養、栄養、心理ケアで予防することが重要です。
小さな違和感を見逃さず、計画的に調整することで、競技力と健康を両立できます。