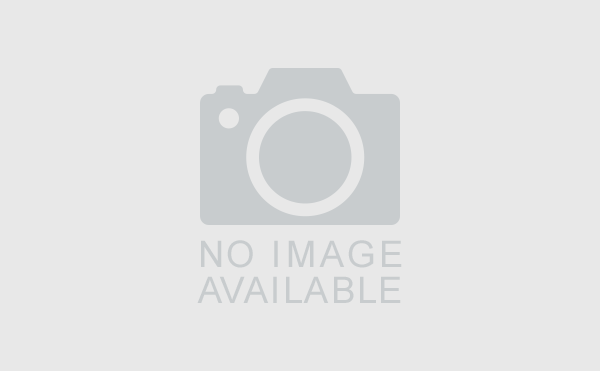練習はパターン化しやすい
学生野球の練習は、どうしても同じ流れになりやすいものです。
ランニング → キャッチボール → トスバッティング → 打撃練習 → 守備練習…
もちろん、これらの基礎練習は土台作りに欠かせません。
しかし、同じことを繰り返すだけでは刺激が不足し、成長が高止まりしてしまうことがあります。
考える野球の重要性
パターン化を防ぐ一つの方法が「考える野球」です。
アウトカウントやランナーを設定し、戦術を話し合う。
試合映像を見て「どう動くべきだったか」をディスカッションする。
こうした取り組みは、試合での判断力や応用力を養います。
ただし、すでに選手自身が主体的に考えて取り組めているチームであれば、現状を大きく変える必要はありません。
大切なのは、チームの実情に合わせて方法を選ぶことです。
場面設定型練習の落とし穴
場面設定型の練習は有効ですが、よくあるのが「決まった選手だけが話し合い、他の選手は受け身」という状況。
また、解決できないまま次のパターンに移ってしまうケースもあります。
せっかくの学びの機会を活かすためには、解決策や気づきを全員で共有し、理解をそろえることが欠かせません。
野球だけに偏らない
考える野球は大事ですが、それにこだわりすぎると日常生活がおろそかになることがあります。
野球選手である前に、一人の人間としての生活の質を高めることが必要です。
- 栄養:しっかり食べて、体を動かすエネルギーと回復の材料を確保
- 休養:十分な睡眠で体と頭をリセット
- 学校生活:授業態度や日常の姿勢も意識する
特に姿勢は、日常生活の影響を強く受けます。
授業中に猫背やだらけた姿勢が習慣化すると、土台となる姿勢が崩れ、キャッチボールやバットスイングといった技術練習にも悪影響が出る可能性があります。
基礎+思考+日常=成長
- 基礎:キャッチボールやバットスイングなどの反復
- 思考:場面設定や映像分析による判断力の養成
- 日常:栄養・休養・学校生活での姿勢づくり
この3つがそろってはじめて、選手は安定して成長できます。
まとめ
- 野球の練習はパターン化しやすいが、考える要素を加えると成長が加速
- 場面設定型練習は、全員で共有することで効果が最大化
- 野球以外の生活習慣や姿勢も、プレーの質に直結する
- 「基礎・思考・日常」のバランスが、長期的な成長のカギ
日々の練習を充実させるだけでなく、生活全体を見直すことが、選手としても人としても成長する近道です。