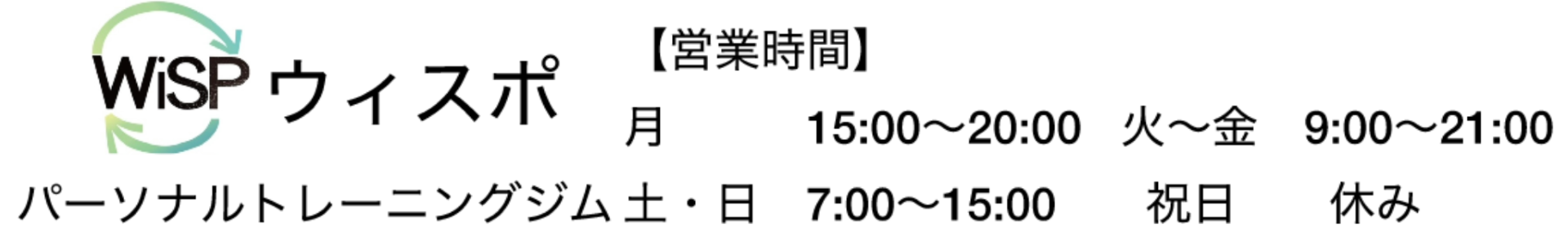ラグビーにおいて、試合後半になるとタックル力やジャンプ力が落ちる現象は非常に一般的です。
しかし、その原因は単なる「疲れ」ではなく、筋持久力の低下と心肺疲労の両面から分析することが重要です。
プロ選手やトップレベルの指導者は、この違いを理解し、トレーニングや戦術に反映させています。
筋持久力低下によるパフォーマンス低下
試合中は、スクラム、ラック、タックル、ラインアウトジャンプなどの高強度の反復動作が連続します。
これにより、筋肉内のATPやクレアチンリン酸、筋グリコーゲンが徐々に枯渇し、筋線維の収縮力が低下します。
筋持久力が不足すると、後半に以下のような現象が起きます。
- タックルの威力が落ちる
- ジャンプの高さが低下する
- スクラムやラックで押し負けやすくなる
この現象は、筋線維レベルでのエネルギー供給能力の限界によるものであり、短時間での回復では完全には補えません。
トレーニング戦略
- 低〜中負荷での高回数トレーニング(スクワット、ランジ、ジャンプスクワット)で筋持久力を強化
- 試合に近い反復動作ドリル(タックル、ジャンプ、スクラム模擬)を組み込む
- 筋線維タイプ(速筋・遅筋)の特性を意識した強化
心肺疲労によるパフォーマンス低下
一方で、心肺疲労も後半のパフォーマンス低下の主要因です。
ラグビーは全力スプリントと短時間休息を繰り返す高強度間欠運動です。
後半になると、酸素供給が筋肉需要に追いつかず、乳酸の蓄積やpH低下が起こります。
この結果、筋収縮効率や神経伝達速度が低下し、タックルやジャンプ力に影響します。
心肺疲労が原因の場合は、
- 息が上がり動作全体のスピードが落ちる
- プレー選択や反応速度も低下する
トレーニング戦略(プロ視点)
- インターバルトレーニング(全力スプリント30秒+軽めジョグ30秒×5〜10セット)で無酸素・有酸素能力を同時強化
- ハーフタイムでの軽い動的ストレッチやジョグで血流を促進し、疲労物質除去を支援
- 心拍変動を測定し、個々の回復力に応じた負荷管理を行う
筋持久力と心肺疲労の見極め方
後半のパフォーマンス低下が筋持久力か心肺疲労かを判断するには、動作と呼吸の状態を観察します。
- 筋持久力不足:呼吸は比較的安定しているが、動作の力が落ちる。タックルやジャンプの高さが低下。
- 心肺疲労:息が荒く、動作全体のスピードや判断力も低下。
この違いを理解することで、選手ごとのトレーニング内容や試合中の交代判断に活かすことができます。
総合的なアプローチ
プロレベルでは、筋持久力と心肺機能を同時に強化するトレーニングが重要です。具体的には、
- 高回数ジャンプ・スクワットで筋持久力を強化
- タックルやジャンプを繰り返すゲーム型ドリルで実戦適応力を向上
- インターバルトレーニングで心肺機能を高め、乳酸耐性を向上
さらに、個々の選手の筋線維タイプや回復能力に応じたプログラム設計が不可欠です。
これにより、試合後半でもタックル力・ジャンプ力を維持し、パフォーマンス低下を最小限に抑えることが可能になります。
まとめ
試合後半のタックル力やジャンプ力の低下は、筋持久力の低下と心肺疲労の両方が影響します。
どちらが主な原因かを見極め、適切なトレーニングを組み合わせることが、学生ラグビーでも成長に直結します。
短時間でも反復動作と心肺トレーニングを取り入れ、筋肉と心肺を同時に鍛えることが、後半でも高いパフォーマンスを維持する最大のポイントです。