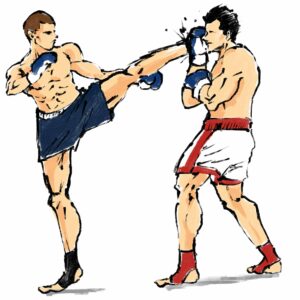短距離・中距離種目は、爆発的なパワーとスピードを高める一方で、高強度トレーニングが頻繁に行われます。
負荷が高い分、オーバートレーニング(過剰疲労)を招くリスクも大きく、パフォーマンス低下やケガの原因になりかねません。
ここでは短距離・中距離選手に特有のオーバートレーニング指標について整理します。
短距離・中距離の競技特性と疲労
- 短距離:最大筋力・瞬発力・神経系への負荷が大きい
- 中距離:スピード持久力を高めるため、無酸素系・有酸素系の両面にストレスがかかる
両者に共通するのは「高強度の質的トレーニング」が中心であり、量を増やしすぎると神経系や筋の回復が追いつかない点です。
オーバートレーニングを示す主な指標
1. 神経系の疲労サイン
- 反応速度の低下(スタートで遅れる)
- スプリントドリルでリズムが重い
- 筋収縮スピードが落ち、接地が長く感じる
→ 短距離・中距離では「質」が重要なため、神経系疲労が最も大きな指標となります。
2. 筋肉・腱の違和感
- ハムストリングやふくらはぎの張りが取れない
- 睡眠後も回復が実感できない
- 関節や腱の炎症感
→ 高強度の繰り返しで出る典型的サイン。ケガの前兆でもあります。
3. 主観的疲労度(RPE)の上昇
- 「スピードが出ない感覚」が数日続く
- 軽いメニューでも極端にきつく感じる
→ RPE(主観的運動強度)は神経系・筋系の両方を反映するシンプルな指標です。
チェック方法
- ジャンプテスト:カウンタームーブメントジャンプ(CMJ)の高さ低下
- スプリントタイム:30mや60mの反復計測でのタイム悪化
- HRV(心拍変動):交感神経優位が続く場合は疲労蓄積の可能性
まとめ
短距離・中距離のオーバートレーニング指標は、神経系・筋肉系の回復具合を中心に確認することが重要です。
単なる疲れではなく「質が出ない状態」が続くときは、練習量を調整すべきサイン。
高強度を積み重ねる競技だからこそ、「やり過ぎを防ぐチェック習慣」がパフォーマンス維持の鍵になります。